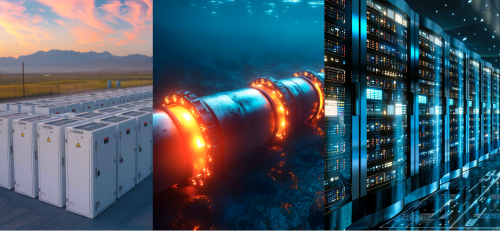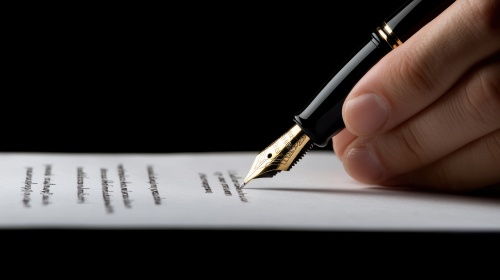イベントレポート/グローバルGX・金融会議札幌
2024年12月16日(月)、17日(日)の2日間、北海道・札幌を舞台に、Team Sapporo-Hokkaidoなど産官学金各セクターが連携して取り組みが進む再エネ開発やGX金融、また北海道を舞台に様々な分野で加速する日本のGX産業について議論が交わされた。




セッションレポート:「GXの風に乗れ ― 再エネフロンティア、北海道」
本セッションでは、北海道がGX(グリーントランスフォーメーション)のモデルケースとして注目される中、再生可能エネルギー事業の可能性と課題が幅広く議論された。

●登壇者
福岡 功慶
資源エネルギー庁 風力事業推進室長
北海道GX推進官
諏訪部 哲也
ユーラスエナジーホールディングス 社長
クレマン・ヘルビグ・ド・バルザック
コペンハーゲン・オフショア・パートナーズ 日本代表
モデレーター 小倉 健太郎
日本経済新聞社 NIKKEI GX編集⾧
セッションの冒頭は、北海道GXの現況に関する話題を中心に進められた。北海道GX推進官という立場で再生可能エネルギー導入を推進する福岡氏は「北海道は風力発電に最適な風況と地形を持っており、特に道北地域では自営送電線や蓄電設備の整備が進んでいる」と述べた。一方で、福岡氏は「系統連系の弱さやインフラ不足が依然として課題」とも指摘し、これらの解決が重要であると強調した。
北海道で風力発電事業を展開する諏訪部氏は「隣接地に、将来的に大量の電力を消費するデータセンターを誘致する試みを始めている」と述べ、北海道における再エネ事業の拡大に向けた需要サイドの開拓が鍵になるとの見解を示した。

地域社会との共生については、デンマークに本拠を置く洋上風力発電事業会社に所属するクレマン氏が「デンマークでは、漁業組合などの地域の利害関係者と緊密に連携し、洋上風力発電プロジェクトへの支持を得ている」と地域コミュニティとの協力が重要であることを示し、「漁業者への雇用創出や地域基金の活用が、地元住民との信頼構築に不可欠」と語った。

さらに、イギリスやデンマークの先進事例も議論の中心となった。福岡氏は「デンマークのリスク軽減策やイギリスの二段階アプローチなど、透明性の高い制度が日本の参考になる」と述べ、こうした国際的な知見を活用したプロジェクトの効率化や安定性を確保する制度改革の必要性を強調した。
モデレーターを務めた小倉氏は、セッションのまとめとして「北海道は再エネ供給地としてだけでなく、データセンターの設置に適した条件を持ち、再エネとDX(デジタルトランスフォーメーション)の融合が期待される」と指摘。北海道を拠点とした持続可能な産業モデルの構築が、日本のGX推進を加速させる鍵になるとの見解で一致した。
地産地消型の新エネルギー開発―水素からバイオメタンまで
本セッションでは、北海道における地産地消型の新エネルギー開発の事例を通じて、持続可能なエネルギー事業の課題と可能性を議論した。特に地域資源を活用したバイオメタンや水素の生成・利用、エコシステム構築の取り組みが中心的な話題となった。

●登壇者
松林 良祐
エア・ウォーター 社長
井出 元郎
よつ葉乳業 常務取締役
喜井 知己
鹿追町長
大島 裕司
日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 サステナブル社会デザイングループ 部長
モデレーター 渡邊 園子
日本経済新聞社上席専任役員

地域の自然資源を活用し、持続可能なエネルギー供給を推進する松林氏は「十勝地方では乳牛25万頭から排出される家畜糞尿を活用し、年間約6万2,000トンのバイオメタンを製造している。このエネルギーは、よつ葉乳業の工場エネルギー供給や、大樹町のスペースポートでもロケット燃料として使用される予定」と述べ、地域経済への貢献と脱炭素社会実現への道筋を示した。
北海道を拠点とする乳業メーカーである、よつ葉乳業の井出氏は「液化バイオメタンを100%使用してもボイラーが安定稼働する技術を確立した。今年5月からは、液化バイオメタンを工場全体のエネルギー源として本格的に利用している」と技術課題も克服し、安定稼働を実現させていることに言及。「酪農家が排出する糞尿を活用し、それをバイオガスに変え、さらに液化バイオメタンとして活用する。この循環型の仕組みが整えば、生乳の安定供給にも貢献できる」と自信を示した。
北海道十勝平野の北西に位置する鹿追町は、国内有数の酪農地帯であり、町全体で約12万トンの生乳を生産している。松林氏は「鹿追町では、家畜糞尿から年間80kgの水素を生成している。この水素は燃料電池車の運用を支え、炭素をカーボンナノチューブとして固定化する技術も採用している。これによりクリーンな水素の生産と副産物の活用が可能となる」と、地域資源を最大限活用したモデルの可能性を強調した。
さらに松林氏は、GX推進に向けて、「規制緩和、事業者への運用支援、需要創出の3つが鍵となる」と指摘。「高圧ガス保安法などの柔軟な対応、価格補填や補助金による支援、供給と需要の好循環を生む仕組みが必要」と述べ、官民連携の重要性を訴えた。

鹿追町の町長である喜井氏は「畜産由来のバイオマス事業には、環境保全や地域雇用促進といった社会的価値が含まれている」と説明。「これらを評価する仕組みや成果連動型のモデルを導入することで、事業の持続可能性を高め、さらなる参画者を巻き込むことができる」と提案した。
北海道が示す地産地消型エネルギー開発の成功事例。地域資源を最大限に活用し、脱炭素化と地域経済の活性化を両立させるモデルとして、他地域への展開や新たな産業創出への可能性が注目されている。
日デンマーク洋上風力発電協力の可能性
デンマークの再生可能エネルギー分野での豊富な経験を背景に、日本との洋上風力発電や水素エネルギーでの協力可能性が議論されたセッション。

●登壇者
ヤール・フリース-マドセン
次期駐日デンマーク大使
ウィリアム・リン
デンマーク・エネルギー庁 日本プログラム室長
トム・ヴァイル・イェンセン ※オンライン・ビデオ登壇
デンマーク保険年金協会 副ディレクター
ラーズ・ウルリッヒ・イェンセン ※オンライン・ビデオ登壇
デンマーク輸出投資基金(EIFO)風力発電チームアソシエイトディレクター
モデレーター 渡邊 園子
日本経済新聞社 上席専任役員
デンマークは1973年のエネルギー危機をきっかけに再生可能エネルギーへの転換を進め、現在では電力の85%を再生可能エネルギーで賄い、その半数以上を風力発電が占める。

「エネルギー政策の進化は長期的な視野が必要」とデンマーク・エネルギー庁のウィリアム氏。
「2030年までに温室効果ガス排出量を70%削減するという目標を掲げていますが、これは決して容易な道のりではない。それでも政府は再生可能エネルギーの利用拡大に全力を尽くしている」とバイオガスやグリーン水素の活用も進めていることに触れた。
次期駐日デンマーク大使であるヤール氏は「デンマークが培ってきたグリーンエネルギーの経験は、日本のエネルギー転換を支援するために非常に有用。両国が協力することで、革新的な解決策を見つけることができると確信している」とデンマークと日本のパートナーシップの意義と、グリーンエネルギー分野での両国の相乗効果への期待を強調した。
デンマーク保険年金協会の副ディレクターであるトム氏は「デンマークの年金基金は2030年までに650億ドルを再生可能エネルギーに投資予定」と説明。その中には日本、特に北海道への投資も含まれるという。
北海道は農業が盛んで人口密度が低いという特性から、「再生可能エネルギー拠点としての成長の可能性が非常に高い」と評価されているとトム氏は続け、加えて、「本州へのエネルギー供給能力を強化することで、日本全体のグリーントランスフォーメーションを支える役割が期待される」ことを強調した。

デンマークで輸出促進や投資支援を進めるラーズ氏は、投資環境整備について、「透明性と規制の予測可能性が重要。さらに、長期的な収益性の確保が国際的な投資を引き付ける鍵」と強調。デンマークでは政策目標の明確化と一貫性が投資促進の要因となっており、このモデルは日本にも参考になると指摘した。
また、風力タービンが「再エネの象徴」とされるデンマークでは、再生可能エネルギーが経済成長を牽引し、地方経済の活性化にも大きく寄与している。こうした成功事例と課題を学ぶことで、日本のエネルギー移行がさらに加速する可能性が議論された。
最後に、モデレーターの渡邊氏は「日本とデンマークの協力は、洋上風力発電や水素エネルギー分野での具体的な進展に寄与するだけでなく、地域経済と持続可能な社会の実現に向けた新たな道筋を示している」とセッションを締めくくった。
パネル討論:国際連携によるGX―気候変動政策の現在地と未来
本セッションでは、GX(グリーントランスフォーメーション)における国際連携の重要性を中心に、日米およびアジアの政策や投資戦略が議論された。モデレーターを務めた日本経済新聞社の滝田洋一氏の進行で、各登壇者がそれぞれの視点から見解を述べた。

●登壇者
ジャヒ・ワイズ 氏
元米大統領特別補佐官(気候政策・金融担当)
レベッカ・ミクラ・ライト 氏
気候変動に関するアジア投資家グループ(AIGCC)代表
エヴァン・フェルシング 氏
在日米国大使館 経済・科学担当公使
モデレーター 滝田 洋一 氏
日本経済新聞社 客員編集委員

元米国大統領特別補佐官として、気候政策や金融分野を担当したジャヒ氏は、「気候変動対策は道義的課題にとどまらず、経済的取り組みである」と主張。米国で実施されている温室効果ガス削減基金(GGRF)について、「クリーンエネルギープロジェクトへの資金提供や排出削減、地域雇用創出が進んでいる」と説明した。また、「グローバルな協力が危機を機会に変える鍵」と述べ、各国が連携して気候課題に取り組む必要性を訴えた。

気候変動に関するアジア投資家グループの代表を務めるレベッカ氏は、アジアにおける気候変動の影響と低炭素投資の現状を解説。「猛暑や海面温度上昇が経済損害を引き起こしている」と指摘し、日本に対してはNet Zero目標達成の重要性を強調。「2050年までに1300億ドルの経済的メリットを生むシナリオ構築と投資を呼び込む政策整備が必要」と提言した。

在日米国大使館で経済・科学担当公使を務めるエヴァン氏は、日米連携の必要性に言及。「インフレ抑制法(IRA)の活用により、パナソニックが米国でEVバッテリー工場に40億ドルを投資するなど、日本企業の積極的な取り組みが進んでいる」と説明。これにより、「クリーンエネルギー分野での事業拡大が実現し、さらなる官民協力が求められる」とした。
セッション全体を通じ、経済成長と環境保全の両立が中心的なテーマとして議論された。政権交代や政策転換の影響を考慮しつつ、産業界、政治、投資家が連携を強化することが、「地球規模の課題解決と新たな経済成長モデル構築の鍵」と確認された。
講演
世界最大規模の資産運用会社の日本法人であるブラックロック・ジャパンの有田氏の基調講演では「GX(グリーントランスフォーメーション)は、経済社会に大規模な変革をもたらす歴史的な投資機会であり、その動きは不可逆的に進行していく」と語り、官民連携を軸とした投資の重要性を強調した。

●登壇者
有田 浩之
ブラックロック・ジャパン 社長CEO
同氏は、「GX推進には今後30年間で4兆ドル(約600兆円)もの投資が必要」と指摘。「高排出セクターと低排出セクターの両方に段階的に資金を配分し、秩序ある移行を目指すべきだ」と述べた。また、ブラックロックが提唱する「エナジープラグマティズム」について、「再エネと化石燃料を併用し、経済と脱炭素を両立させる現実的な政策が求められる」と説明した。
インフラ投資においては、同社が買収した世界最大の独立系インフラ投資マネージャーGIP(グローバル・インフラ・パートナーズ)に触れ、「エネルギー、運輸、デジタル分野を中心に約26兆円規模の投資プラットフォームを構築した。これにより、日本のGX関連インフラ事業にも積極的に貢献していく」と展望を示した。
さらに、「官民連携を支えるブレンデッドファイナンスが鍵になる」と述べ、公的セクターが民間のリスクを補完する仕組みの必要性を指摘。「コーポレートガバナンスや投資家との対話を通じ、持続可能な成長を支えるエコシステムを構築していく」と締めくった。
サステナブルファイナンス:GX国際金融都市へ向けた札幌のポテンシャル
2日間のフォーラムを締めくくる最後のセッション。札幌がGX(グリーントランスフォーメーション)の推進拠点として注目される中、本セッションでは北海道が持つ潜在力と国際的視点からの可能性が議論された。

●登壇者
池田 賢志
金融庁 総合政策課長
ショーン・キドニー
クライメートボンド・イニシアチブ CEO
バート・ハンター
コネチカット・グリーンバンク 最高投資責任者(CIO)
モデレーター 高田 英樹
GX推進機構

金融庁の総合政策課長である池田氏は、「北海道が内包するGX資源と機会は産業革命時代に匹敵するほど大きい」と指摘。再生可能エネルギーへのシフトを図る中で、札幌が担うべき役割の重要性を強調した。また、「銀行業務から資産運用ビジネスへのシフトが日本経済に必要」と述べ、日本の預金や資産を世界の投資に循環させる重要性に触れた。さらに、札幌が「リスクキャピタルを動かす拠点としての機能を高めるべき」と提言した。

バート氏は、自らが最高投資責任者(CIO)を務める米国初のグリーン・バンクの実例を挙げ、「GXを成功させるには、明確なメッセージと債券保証、税制優遇、グリーンファンドのような特別商品が必要」と提案。「UK、オーストラリア、日本のグリーンファイナンス組織とともに、グリーンバンクネットワークを構築してコンセプトを広める」と国際ネットワークの重要性に関しても発言。

気候変動対策に必要な資金調達を促進することを目的とした国際的な非営利団体のCEOであるショーン氏は、「グリーンボンド市場はこれまでに5.5兆ドルの可能性を生み出してきた」と述べ、日本の課題を新たな産業機会として捉える視点の重要性を強調した。さらに、「気候変動対策推進とレジリエンスを基盤とした社会システムの構築が必要」と提言した。
モデレーターの高田氏は、「金融企業が仲介者としての役割を極めること、投資資産や流動性を高めること、セクター間の協働推進力を強化すること」が今後の成長の鍵であると締めくくった。

フォーラム終了後、来場した日本国内のシンクタンクからも「データセンターや半導体など先端産業の発展に繋がるGXのシナリオ提示など、世界でも最先端の事例紹介であり意義深かった。札幌でこうした国際感覚に溢れ、GXを通じた総合価値を創出するために産学官が終結し、議論を深めたことは将来具体的な投資成果として結実するであろうと確信することができた」という声が上がり、大変意義深く、価値ある2日間であったことを感じた。
多くの登壇者が、経済価値だけでなく、地域社会との共生を通じた社会価値の追求ということにも触れられていたことも印象深く、同氏は「この共生(ともうみ)の精神があれば、複雑化する社会変革の中においても北海道&札幌は大きなGX投資成果を生み出すことが出来るであろうと考えている」と希望を滲ませていた。
なお、フォーラムの初日には、クライメート・ボンド・イニシアチブ、北海道、札幌によるGX推進と地方創生に関する共同声明も発表された。
https://tsh-gx.jp/engagement/jointstatement/